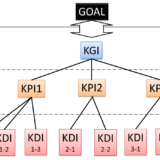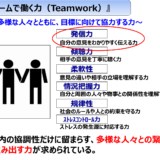どうもです!これまで整理してきた社会人基礎力の12個の各スキルに対し、より確実に鍛えるための日々の行動リストを紹介しています。
スキルを身につける上で必要な要素を抽出し、それぞれに対してどのような行動がレベルアップに繋がるかをリスト化して考えていきます。
行動リストが日常の中で具体的に行動に移す上での皆様の助けとなりましたら幸いです!

行動リストを全て実施するのは非現実的です。特に取り組むべきポイントを絞り、確実に日々の行動に移しましょう!慣れにもよりますが、個人的には特に重要と感じた3つに絞るのがオススメです。
今回のテーマは創造力です!
創造力とは?
創造力とはシンプルに新しい価値を生み出す力として定義されます。新しいアイデアを生み出す力、既存の物事を新たな視点で捉える力、そしてそれを形にする力のことを指します。
創造力と聞くと、アーティストなどの一部の人に必要な力と感じるかもしれません。しかし、ビジネスパーソンや、学生など、あらゆる人が活用でき、鍛える意義のあるスキルです。
具体的には以下のような要素が含まれます。
- 発想力:枠にとらわれない自由なアイデアを生み出す力。
- 応用力:既存の情報や技術を組み合わせ、新たな価値を創造する力。
- 実現力:新しいアイデアを形にする、新たな価値を表現して届ける力

創造力があることによるメリットや各要素についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
それぞれの要素を抑えながら、どのような行動が創造力アップに繋がるのか考えていきましょう!
創造力を鍛えるために必要な要素と行動リスト
1-1.発想力:発想量を増やす
発想力とは、枠にとらわれない自由なアイデアを生み出す力を指します。創造力の元となる閃きやアイディアを生み出す力となります。
発想力を鍛えるにはまず量に着目することを推奨します。量をこなすことで、発想の幅が広がりアイデアの自由度も上がるので結果として質の向上も期待できます。
発想のベースとなる量を増やすための日々の取り組みを整理します!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 毎日アイデアメモを3つ書く | 習慣化で発想量を増やす | 出勤前に3つアイデアを書き出す | 3か月で200以上のアイデアを蓄積 |
| 数字目標付きブレスト | 量産思考を身につける | 会議で最低10案を出すと決める | 多数のアイデアから良案を抽出する力をつける |
| 無関係ワード連想法 | 思考の幅を広げる | ランダムな単語から3つの発想を出す | ・異分野融合型の発想を自然にできるようにする ・異分野融合型の発想を3か月で2つ以上仕事に応用 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| メンバー全員から必ず発言を引き出す | 多様なアイデア収集 | ・会議で全員に最低1案を求める ・ファシリテーションをメンバーに任せる | チームから常に豊富なアイデアが出る文化を育てる |
| 否定しないルールの徹底 | 安心感が広がり、アイデア数が増える | ・まず全て「ありがとう」と受け止める ・会議やディスカッションのルールを明文化する | ・アンケートで心理的安全性の評価を30%以上アップ ・会議、ディスカッションでのメンバーの発言量30%増 |
| ブレインストーミングを使いこなす | 適切な場面でブレインストーミングを活用しチームの発想量を強化する | ・ブレインストーミングが有効な場面を把握し積極的に活用する ・ブレインストーミングを実施する上でのルールを守る | ・ブレインストーミングが有効な場面での開催確率100% ・開催したブレインストーミングより出た有効な改善策を1年間で平均2個以上/回 |
| 発想数ランキング制度 | ゲーム感覚で発想促進し、継続的に発想量を高めるチーム風土をつくる | アイデア提出数を可視化する | ・3か月で全メンバーよりチーム改善のアイディアを最低1つ以上提案 ・半年間でチーム全体のアイディア数1.5倍に |
ブレインストーミングのコツ
ブレインストーミング自体は有名ですが、実際やってみて苦戦した経験はありませんか?取り組んでみると中々難しいですよね。
発想量強化につなげるには有効な場面でルールを守って実施することが重要です。ブレインストーミングのコツとして、有効な場面、実施する上でのルール、そして、さらに効果を高めるポイントを再確認しましょう!
有効な場面
まず、ブレインストーミングを実施するのに有効な場面は下記があげられます。このような場面ではブレインストーミングを積極的に活用し発想量を強化しましょう!
| ブレストが役に立つ場面 | 具体例 |
|---|---|
| ① 新しいアイデアを生み出したいとき | 付加価値:新商品・サービスの開発、新規事業の立案 業務効率:社内の効率化、コスト削減、働き方改革 |
| ②チームの意見を広く集めたいとき | 企画会議、マーケティング戦略の検討 |
| ③ 問題解決のヒントを得たいとき | トラブル対応策の検討、新しい戦略の策定 |
ブレインストーミングを実施する上でのルール
折角開催しても、ルールが不適切ではブレインストーミングは効果がありません。事前に整備して参加者に周知して守ってもらいましょう。
| ブレインストーミングを実施する上でのルール | 詳細・具体例 |
|---|---|
| ① 批判・否定は禁止(心理的安全性の確保) 心理的安全性が気になる方は過去記事もご参照ください | どんなアイデアでも歓迎し、批判しない。「それは無理」「ありえない」はNG! |
| ② 質より量を重視 | アイデアの数をとにかく多く出す(質の高いアイデアは量から生まれる) |
| ③ 自由奔放な発想を歓迎 | 突飛なアイデアや一見非現実的なものも受け入れる |
| ④ アイデアを組み合わせて発展させる | 他人のアイデアを参考に、新しい視点を加えて発展させる |
| ⑤制限時間を設ける | 「10分で20個のアイデアを出す」など、時間を制限することで発想に集中できる |
ブレインストーミングを実施する上でのポイント
また、下記のようなポイントを抑えることで、アイディアが出しやすい環境が整備できます。
| ブレインストーミングを実施する上でのポイント | 詳細・具体例 |
|---|---|
| ① 目的を明確にする | 「新商品のアイデアを出す」「業務改善策を考える」など、テーマを明確に設定し参加者に共有する(自由と言っても脱線はしないように) |
| ②キーワードやフレームワークを活用する | オズボーンのチェックリスト(転用・変更・結合など)を活用して発想を広げる |
| ③ 付箋やホワイトボードを使う | 参加者が見える形でアイデアを並べることで、発想をつなげやすい。また記録もしやすくやりっぱなしになりづらい。 |
| ④ 少人数(4~6人)で実施する | 多すぎると意見が埋もれ、少なすぎるとアイデアが広がりにくい。適度な人数での実施が必要。 |
| ⑤ ファシリテーターを立てる | 議論が停滞しないように、進行役がテーマやルールを管理する。必要に応じて、偏見や制限を取っ払う問いかけなどで議論を活性化する。例:「もし予算が無限なら?」 |
| ⑥個人ワークの時間や事前ワークを活用する | いきなり集団ワークをすると声の大きい意見に流されやすかったり、他人の様子に気を取られ発想に集中できない場合がある。対策として個人で発想に専念する時間を設ける。 |

場面によってはルール(必須の条件)とポイント(取り入れることで改善を期待できる点)は変わります。
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| アイデアスケッチ習慣 | ドラフトよりアイディアを生み出す、頭の中のアイディアを形にする | 毎回5分でスケッチを描く | 1年で作品アイデア集を作る |
| 制限時間付き発想 | 集中して数を出す | 10分で思いつく限り書き出す | ・10分間での発想数を3か月で20%アップ ・新しいアイディアの採用数を半年で30%アップ |
| 既存作品を改変する | 独自作品のバリエーションを広げる | 好きな作品を5通りにアレンジ | ・3か月で新しい作風に3つ以上挑戦 ・1年間で作風のレパートリーを3つ以上増やす |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家族でアイデアラッシュ | 家庭課題の解決 | ・1カ月に1回アイディアを出し合う時間を設ける ・ホワイトボードなどを用いて認識の共有を強化する | 家族で発想を楽しむ習慣化 |
| 子どもとの発想ゲーム | 発想量を自然に増やし創造性を伸ばす | ・「もし〇〇だったら?」という問いかけを1日1回する ・子供からの質問に丁寧に回答する | 子供から新しい発想を話してくれる回数を半年で2倍に |
| 家事の代替案出し | 家族が発想を生活に応用できる力をつけ、日常を改善する | 1つの家事に5つのやり方を考える | 3か月で家事の改善回数3個以上 |
1-2:発想力:発想の質を上げる方法
発想量の次は発想の質に着目です!より良いアイディアを出すための日頃の行動に着目します。
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 仮想条件で検討 | 制約の中で精度を上げる | ・「予算が半分なら?」で考える ・「納期が来週だったら?」とし解決策を考える | 半年間で30以上の制約条件付きアイデアを出す |
| 他業界事例の応用 | 視点を広げる | 週1回異業種の事例を調べる | 年間で50事例を分析・応用アイデアを10件提案 |
| アイデアの3段深掘り | 表面的発想を防ぐ | 出した案を「なぜ?」で3回掘る | 半年で100件の深掘りアイデアを記録 |
制約を考える視点
制約は発想の幅を狭める印象があるかもしれません。しかし、条件を絞り追い込むことで情報を整理しやすくなったり、新たな課題発見に繋がり、発想のトリガーになりえるのです。
個人的に制約をいきなり考えるのは難しい印象です。でも、訓練しないと身に付かないもの・・・。
そこで、仮想条件を検討する視点をいくつか追加で紹介します。仮想条件により制約を考える第一歩としてください!
- リソース制約
予算・人員・時間などが限られている状況を設定する。 - 環境制約
物理的環境や社会的状況(自然条件、法律、文化など)を制約として考える。 - 機能制約
「必ず1つの機能に絞る」「2つの機能を統合する」などの機能面での制限。 - ターゲット制約
「高齢者だけ」「子供だけ」「初心者だけ」など対象を限定する。 - 形式・手段制約
「必ずオンラインで完結」「紙1枚にまとめる」「道具を1種類だけ使う」など、方法や形を制限する。
制約を考える上での具体例
更に具体例を下記に掲示します。皆様の業務への応用の参考になれば幸いです!
- 予算を半分にしたら?
広告費を削減し、口コミやSNSを活用した低コスト施策を考える。 - 時間を3分の1に短縮するなら?
会議を15分以内にするために事前に意見を共有し、当日は意思決定だけ行う。 - 対象を子供に限定したら?
小学生でも使えるシンプルなインターフェースを考案する。 - 道具を1つしか使えないなら?
フライパン1つで朝昼晩の料理を作る工夫を考える。 - 環境負荷ゼロを前提にしたら?
プラスチック包装を使わず、再利用可能な素材やリフィル方式を採用する。

制約を加えた中でどう工夫するかという発想を刺激するのは物語や企画などのエンタメでも見られるアプローチですね。
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| メンバーに評価視点を与える | 質を磨く観点を共有 | 「独創性・実現性・影響度」で評価する | 半年で提出アイデアの70%以上を3観点で評価済みにする |
| 具体化の問いかけ | 思考の整理を促し実現可能性を高める | ・「実行するなら何が必要?」と聞く ・3回問いかけメンバーの考えを深掘り/整理する | ・年間で20件の具体的実行プランをチームから引き出す ・メンバーの75%以上が課題発見力/実行力の向上を実感 |
| 試作品文化を作る | アイデアを形にして検証するスピードを高速化しアイデアを磨く | ・1週間に1回以上メンバーに小さな挑戦を促す ・1週間に1回以上メンバーの取り組みを検証/振り返る機会を設ける | ・年間で少なくとも10件の試作品・PoCを実施 ・メンバーの80%以上が仮説設定&検証力アップを向上 ・仮説設定&検証のコツをナレッジ化して共有 |
リーダーにおける制約条件の活用
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| ◆リソース制約 限られた予算で最大効果を出す施策をチームと検討する | 効率的な資源活用とコスト意識の強化 | 毎週の会議で「低コストでできる工夫」を1案出す | 半年で経費削減率10%、かつ成果指標(売上や満足度)を維持・向上 |
| ◆環境制約 法規制や市場環境の変化を前提にしたシナリオを考える | 柔軟性とリスク対応力の強化 | 毎月1回、規制や市場トレンドに関する情報を共有 | 1年以内に「新規規制対応による業務停滞ゼロ」を達成 |
| ◆機能制約 プロジェクトで「最小限の機能(MVP)」を定義して実行する | 無駄を削減し、素早く仮説検証する文化を育成 | 新企画は必ず「MVP」を設定してリリース | 1年以内に試作→検証→改善のサイクルを従来比で2倍速化 |
| ◆ターゲット制約 顧客や部下の中で「特定層」に絞った施策を考える | 成果の出やすい部分に集中する | プロジェクトごとに「優先ターゲット層」を必ず設定 | 半年以内に主要ターゲットの満足度80%以上を達成 |
| ◆形式・手段制約 会議は必ず「15分・資料1枚」で実施する | 生産性向上と意思決定スピードの強化 | 会議前に要点を1枚にまとめて共有 | 3か月で会議時間を30%削減し、意思決定までの期間を短縮 |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 他人のフィードバック活用 | 視点を増やす | SNSや友人に感想を聞く | より洗練された作品に仕上げられる |
| アイデアを3案比較 | 質的選択を意識 | 同じテーマで3案出し比較 | ・作品のオリジナル性を高める ・作品に新しく取り入れたアイディアを半年で3個以上 |
| プロの事例分析 | 質の基準を学ぶ | 週に1作品を分析する | ・自分の作品レベルを客観的に上げる ・分析より自分の作品に採用したアイディアもしくは技術を半年で3個以上 |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家族アイデアを評価する基準を決める | 選択肢の質を上げる | 「楽しさ・実用性・負担の軽さ」で点数付け | 家族が合理的に選べる力を持つ |
| 実際に試す→改善 | 質の検証を繰り返す | 家族アイデアを1つ実行し改善点を話す | 家庭内で「トライ&エラー文化」が根付く |
| 他家庭の工夫を参考 | 視野を広げる | SNSや知人から工夫を聞く | 3か月で新しく試す工夫を3個以上 |
2.応用力
応用力とは、 既存の知識や経験を活かして、新しいアイデアを発展させる力です。
既存の技術やアイデアの組み合わせでも、新しい付加価値が生み出せるのであれば、それは立派な創造力となります。
以前の記事で紹介したオズボーンのチェックリストとアナロジー思考も組み合わせながら推奨行動を整理します!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 他部署の事例やノウハウを自分の業務に応用する | 視野を広げ、効率的な業務改善を行う | 月3回、他部署の成功事例を分析 | 半年で15件以上の事例を活用し、2件以上で業務改善に成功 |
| 過去の失敗から改善策を抽出し、別プロジェクトに応用する | 失敗を成長の資源に変える | 過去の失敗3件を洗い出し改善案を考える | 四半期ごとに失敗10件を振り返り、3件以上を施策に反映 |
| 小規模実験を応用展開する | 成功パターンを横展開する | 毎月1つ小実験を計画 | 半年で3件以上の成功パターンを他案件に応用 |
| アナロジー思考:異業種や趣味から発想を借り、自分の課題に当てはめる | 異分野の知見から新しい解決策を得る | 月1回、異業種の事例を調査し適用 | 半年で6件以上、異業種事例を業務に応用 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 部下の強みを他業務に応用する | 個々の能力を最大限発揮させる | 毎週1人の強みを確認 | 半年で全員の強みを1回以上活用 |
| 他部門のノウハウを取り込む | 組織横断の力を高める | 月1回、他部門との情報交換を実施 | 1年以内に他部門連携による成果創出を3件以上 |
| チーム成功事例を標準化 | 組織全体の底上げ | 成功事例を必ずドキュメント化 | 半年で3件以上を社内標準プロセスに反映 |
| ピンチを学習機会に変える | 危機対応力を強化 | 問題発生時に必ず「学び」をチームで振り返り言語化 | 1年で同種トラブルの再発率を30%削減 |
| オズボーンのチェックリストを活用 | 固定観念を外し、発想を多角化する | 月2回、定例会で活用 | 1年で10件以上の改善策を実行 |
| アナロジー思考:他業界のベストプラクティスを取り込み、チーム改善に応用 | チームに外部の発想を取り入れる | 四半期に1回、異業界の事例を紹介 | 半年で4件以上を議論し、1件以上を実践に適用 |
オズボーンのチェックリスト
オズボーンのチェックリストとは発想を広げて応用力を鍛えるためのフレームワークです。
具体的には下記の9つの視点で発想を広げるための問いかけをするリストとなっています。こちらを会議やアイディア出しの際に活用することで応用力の強化が期待できます。
| 視点 | 質問例 | 活用のポイント |
|---|---|---|
| 1. 転用(Put to other uses) | 他の用途に使えないか? | 既存のものを新しい用途に応用する |
| 2. 適応(Adapt) | 似たものからヒントを得られないか? | 他の業界や技術を参考にする |
| 3. 修正(Modify) | 色・形・機能を変えたらどうか? | 部分的に変更して新しい価値を生む |
| 4. 拡大(Magnify) | 大きくしたら? 量や時間を増やしたら? | スケールを大きくすることで新たな価値を生む |
| 5. 縮小(Minify) | 小さくしたら? シンプルにしたら? | コスト削減や携帯性向上につながる |
| 6. 代用(Substitute) | 他の素材・技術・方法に置き換えられないか? | 代替材料や新技術の活用を考える |
| 7. 再配置(Rearrange) | 順番・レイアウト・仕組みを変えたら? | 効率化やユーザー体験の向上を図る |
| 8. 逆転(Reverse) | 逆にしたらどうなるか? 役割を入れ替えたら? | 立場を変えて考えることで新しい視点を得る |
| 9. 結合(Combine) | 他のものと組み合わせたら? | 異なる要素を掛け合わせて新しい価値を生む |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 他の趣味の知識を取り入れる | 新しい視点で楽しみを広げる | 毎週1回、他ジャンルに触れる | 半年で趣味の幅を2つ以上拡大 |
| 過去の失敗を工夫に活かす | 試行錯誤の積み重ねで成長する | 練習後に改善点を1つ記録 | 1年で同じミスの発生率を半減 |
| アナロジー思考:趣味の経験を比喩的に仕事や学習に結びつける | 趣味と実生活を統合的に学ぶ | 月2回、日記にアナロジーを記録 | 半年で12件以上を仕事に応用 |
3.実現力
最後に紹介するのは実現力についてです。アイデアが効果を発揮するには実現する力が必要になります。
考えを持っているだけの人と実際に行動する人では達成できることは大きく異なります。
この力は実際に挑戦しないと中々身に付きません。アイデアを実現させる力を身につけるのにどのような行動が役に立つのかを見ていきましょう!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 小さな試作(プロトタイプ)を作る | アイデアを具体化して課題を発見する | 毎週1つは紙やデジタルで簡単な形にしてみる | 6か月以内に3件以上の試作品を業務で実用テストする |
| 提案し意見をもらう | 客観的な視点を取り入れ改良しながら、アイディアや考えをアピールする(+仲間を増やす) | 上司や同僚に週1回はアイディアや考えを共有し、フィードバック・意見をもらう | 半年で10件以上の改善提案を反映させる |
| 小さな成功体験を積む | 実現力の自信を育てる | ・毎日アイディア実現のためのアクションを1つ以上する ・毎日1回「できたこと」をメモする | 1年以内に成功事例を5件以上実現 |
| データや数値で検証する | 成果を可視化して説得力を高める | ・施策実施時は計画段階で検証のための数値(Indicator)を設定する ・施策実施後で数値設定の妥当性も含め結果を検証する | ・検証のための数値設定が妥当である割合を80%以上 ・1年以内に3件以上の業務改善効果を数値で証明する |

何でもいいから形をするというのは実現力の鍵と感じます。いつまでも悩んでいる人は物事が中々前に進まない印象です。進めながら考える姿勢の方が必要な情報も手に入り解像度が上がるのでアイディアの質も向上し創造力が強化されます。まずは紙やスライドに考えをまとめることからでもいいので、アウトプットしてみることを強く推奨します!
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| メンバーに役割を割り振る | アイデアをチームで形にする | ・実行タスクへ必ず役割を明確にする ・メンバーの関心を1on1等で確認 | ・アイデア提案・実現へのチーム参画率100% ・6カ月以内にチームで実現したアイデア数を5個以上 |
| 実現のためのスケジュールを作る | 実行プロセスを明確化する | 各プロジェクトで必ず週単位のスケジュールを作成する | 1年以内に主要プロジェクトの90%以上を期限内に完了 |
| 成果を見える化する | チームのモチベーションを高める、また小さな成功体験をチームで共有 | ・毎週の定例会で進捗と各メンバーの貢献を共有する ・月2回チーム内で成果を共有 | ・半年以内に3件以上の成果を社内発表にまとめる ・アンケートで社内メンバーのモチベーションを3か月で30%アップ |
| 失敗を許容する環境を整える | チャレンジの心理的安全性を確保する | ・メンバーがチャレンジしたら賞賛する ・メンバーのチャレンジに対して必要な支援(道具的、情報的、情緒的、評価的&機会提供)をする ・月1回は「失敗から学んだこと」を共有する | 1年以内に新しい取り組みを5件以上チームで試す |
| 外部の知見(書籍・セミナー)を紹介し、アイディア実現を後押しする | 知見を共有しアイデア創造・実現の後押しをする。また共有の文化を作る。 | ・月1回、アイディア実現に役立つ情報を紹介 ・意欲的なメンバーに知見の収集と共有を依頼する | ・1年以内に紹介した知見を活用した提案を2件実現に導く ・メンバーが知見を共有するようになる |
アイデア実現を後押しするためのフィードバック
リーダーとして重要な役割としてメンバーへのフィードバックがあります。
適切なフィードバックにより、メンバーの行動の方向性の決定、スキルアップ、モチベーションアップなどに繋がります。
メンバーの能力や成果を上げ、チームのポテンシャルを最大化するためのフィードバックのコツを紹介します。
フィードバックのコツ
| コツ | 目的 | 具体的なFB例 | 行動の上での注意点・コツ |
|---|---|---|---|
| ポジティブな点から始める | 提案者のモチベーションを高め、アイディアを前向きに捉えさせる | 「この視点は新しくていいね」「具体性がある部分が強みだね」と最初に肯定する | 形だけの褒め言葉ではなく、本当に良いと思った点を具体的に伝える |
| 改善点を建設的に示す | 提案をより実現性の高い形に導く | 「コストの面では工夫が必要かもしれないね。例えば~はどうだろう?」 | 「ここがダメ」と否定せず「より良くするには?」の姿勢で伝える |
| 実行可能性を一緒に検討する | アイディアを行動に移す流れを作る | 「このアイディアを小さく試すなら、どのステップが最初にできそう?」と質問する | リーダーが答えを出すのではなく、提案者に考えさせる問いかけを重視 |
| 数字や期限を伴う視点を加える | 実現に向けた具体性と責任感を持たせる | 「3か月以内に効果を測るとしたら、どんな指標を使える?」 | 数字や期限は強制せず、提案者と一緒に決めて合意形成 |
| 実現に必要なリソースや協力者を提示する | 実行へのハードルを下げ、前進を後押しする | 「この点は他部署の協力が必要だから、私から話をつないでみよう」 | 提案者に全責任を背負わせず、リーダー自身も支援する姿勢を見せる |
| 定期的にフォローアップする | 提案が放置されず、改善と前進が続く状態を維持する | 「来週のミーティングで進捗を確認しよう」「困ったらすぐ相談して」 | 監視ではなく伴走の姿勢を示し、信頼関係を維持する。 |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 作品を形にして発表する | 完成の喜びと改善点を得る | 週1回はSNSや仲間に成果を発表する | 半年以内に10件以上の作品を公開する |
| 道具や手法を工夫する | 表現力を広げる | 月2回は新しい技法や道具を試す | 1年以内に3つ以上の新技法を習得する |
| 他人と共有・コラボする | アイデアを発展させる | 月1回は仲間の作品を参考に意見交換する | 1年以内に2件以上コラボ作品を完成させる |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家事や生活の工夫を試す | 生活を快適に改善する | 週1回は新しい工夫を導入する | 半年以内に5件以上の生活改善を定着させる |
| 家族の意見を取り入れる | 家族全員の満足度を高める | 月1回は家族会議やアンケートを実施する | 1年以内に家族の満足度80%以上を達成する |
| 小さなイベントを企画する | 楽しさを形にして共有する | 季節ごとにイベントを企画・実施する(年4回) | 1年以内に家族イベントを4回以上開催する |
終わりに
「創造力」は特別な才能ではなく、誰もが鍛えることのできるスキルです。
日常生活の中で意識的に練習することで、あなたの仕事や人生に新しい視点と可能性をもたらしてくれます。
まずは小さな一歩から、「今日何か新しいことに挑戦してみる」という行動を始めてみませんか?今回の行動リストが皆さんの創造力強化に役立ちましたら幸いです!
それではまた次の記事で!