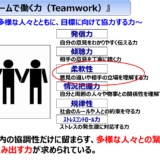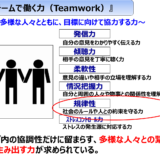どうもです!これまで整理してきた社会人基礎力の12個の各スキルに対し、より確実に鍛えるための日々の行動リストを紹介しています。
スキルを身につける上で必要な要素を抽出し、それぞれに対してどのような行動がレベルアップに繋がるかをリスト化して考えていきます。
行動リストが日常の中で具体的に行動に移す上での皆様の助けとなりましたら幸いです!

行動リストを全て実施するのは非現実的です。特に取り組むべきポイントを絞り、確実に日々の行動に移しましょう!慣れにもよりますが、個人的には特に重要と感じた3つに絞るのがオススメです。
今回のテーマは情況把握力です!
情況把握力とは?
情況把握力とは「自分と周囲の人びとや物事との関係性を理解する力」を指し、情報を収集して自分事に落とし込み自分の置かれている状況や情報を正確に捉え、何をすべきかを判断する力が求められます。
これは以下のような能力の組み合わせによって成り立ちます。
- 情報収集力:状況に関連する事実・データ・人の動きなどを的確に捉える力。
- 分析・整理力:集めた情報を構造化し、優先順位や因果関係を把握する力
- 俯瞰力・適応力:自分の視点に偏らず全体を広く捉え、変化に応じて視点や行動を調整する力
情況把握力は、単に目の前の出来事を見るだけでなく、「今の状況がどのような意味を持つのか」、「どのような影響を及ぼすのか」を考えることに繋がります。その結果、適切な判断や行動が可能になります。

情況把握力についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
情況把握力を鍛えるために必要な要素と行動リスト
それでは情況把握力を鍛えるにはどのような方法があるかを考えてみましょう!
3つの視点(情報収集力・分析整理力・俯瞰力と適応力)に基づき、それぞれの鍛え方・ポイント・注意点・具体例を詳しく紹介していきます!
今回は更に情報収集力を①-1目的の明確化&仮説設定、①-2適切な情報源の活用、分析整理力を②-1フレームワークを活用した整理、②-2関係性の分析&優先順位設定に分けてより詳細にしました。
また、情況把握力をどう判断・決断力に活かすかという視点も追加しました!皆様のスキルの強化に役立てば幸いです!
①-1 情報収集力:目的を明確にする/仮説を設定する
まず大事となるのが情報収集力です。情報がなければ情況把握はできません。
一方で闇雲に情報を集めればいいというものではありません。どんなに情報が多くても素通りしていては意味がありませんし、情報が多すぎると処理しきれません。
効率的に情報を収集する上で重要なのが目的の明確化です。目的を明確化することで必要な情報に絞って収集できますし、収集した情報への感度も高まります。
また、目的を明確化する上で役に立つのが仮説設定です。仮説を設定することでどのような情報が必要になるかが明確化し、情報収集の目的もより具体化します。
情報収集の主な目的
因みに情報収集の主な目的は下記となります。
| 分類 | 目的 | 具体例 |
|---|---|---|
| 課題特定 | 解決すべき問題を特定するため | 社内の課題を社員よりヒアリング、顧客アンケートにより要改善点を確認 |
| 問題解決 | 問題の原因や対応策を特定するため | 顧客満足度低下の原因調査、トラブルの再発防止策の探索 |
| 意思決定 | 複数の選択肢から最善を選ぶため | 新製品の仕様をA案/B案から選ぶ、投資先の選定 |
| 提案・企画 | 新たな提案や企画を立てる材料を得るための情報収集 | 新規事業アイデアの構想、広告キャンペーンの企画 |
| トレンド把握 | 市場や業界、社会の変化を察知するための情報収集 | DX関連技術の動向、働き方改革の影響 |
| リスク管理 | リスクや脅威の発見・予防のための情報収集 | 為替や法律の変更の兆候、クレームの前兆の把握 |
| 競争分析 | 競合企業の動向を知り、自社戦略に活かす情報収集 | 同業他社の新商品、価格戦略、プロモーション内容 |
| 評価・効果測定 | 実施施策の成果や影響を確認するための情報収集 | マーケ施策後の売上変化、研修後の社員の変化 |
複数の目的が重なるケースも多くあるのでMECEにこだわる必要はありません。その中で主目的と副目的を切り分けると優先順位をつけやすくなり情報収集の質と効率が上がります。
この目的リストも踏まえて目的の明確化と仮説設定という観点で行動リストを見ていきましょう!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 仕事の開始時に「このタスクの目的」を一文で書く | 業務の方向性を明確にしてムダを防ぐ | 毎朝のToDo作成時に各タスクの目的を明記(5回/週) | ・3ヶ月後に目的不明でやり直しとなる業務を50%削減 ・半年で情報収集の時間を30%削減 |
| 案件ごとに「主目的」と「副目的」を整理 | 情報収集の優先度を明確にする | 案件開始時に主副目的を分ける(全案件で実施) | 半年以内に、上司レビュー時の目的修正指摘を30%減少 |
| 仮説メモを事前に作成し、収集後に検証 | 情報の方向性を定め効率化する | 各リサーチ開始時に3つの仮説を立てて記録 | ・3か月で仮説検証可能率80%以上 ・6ヶ月後、仮説→実証で一致率70%達成 |
| 週次で「今集めている情報の目的」を棚卸 | 情報過多を防ぎ焦点を保つ | 毎週末に情報リストを整理し目的外を削除 | 3ヶ月後、情報整理時間を20%短縮 |
| 同僚に目的を説明して客観視点を得る | 自分の目的のズレを防ぐ | 週1回、チームミーティングで説明練習 | 半年後、説明力アンケートで平均4.0点以上獲得(5点満点) |
| 目的を定期的に更新(案件の進行で変化に対応) | 状況変化に応じて柔軟に対応 | 重要案件ごとに月1回目的を見直す | 1年後、目的変更後のリカバリー率80%以上達成 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| メンバーのタスクに対して「目的を共有」 | チーム全体の方向性を揃える | 毎朝ミーティングで1分目的確認を行う | 3ヶ月後、チーム内目的認識ずれを50%減少 |
| 目的が曖昧な時に「なぜやるのか?」を3回深掘る | 本質的な目的を明確化 | 週2回以上、ミーティング中に「なぜ?」を投げかける | 半年後、目的不明確な対応・報告書を0にする |
| 仮説思考でチーム課題を分析 | 問題解決をスムーズにする | 各会議で「仮説→検証→修正」のサイクルを回す | ・3か月で仮説検証可能率75%以上 ・半年でプロジェクト成功率+20%向上 |
| メンバーに目的設定を任せ、振り返る | 自主性と理解力を高める | 月1回、メンバー主導で目標設定を行わせる | 1年後、目的自己設定率100%達成 |
| 部署間会議前に「この会議の目的」を事前共有 | 無駄な議論を防ぐ | 会議案内時に目的1文を添付(全会議) | 3ヶ月後、平均会議時間を20%短縮 |
| チーム全体で仮説を立て検証する文化を育てる | チームの洞察力・柔軟性強化 | 月次振り返りで仮説検証結果を共有 | 半年後、チーム内提案採用率を30%増加 |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 趣味の活動前に「今日の目的」を1つ設定し、目的達成度を振り返る | 活動の充実度を高め、成長実感を得る | ・趣味開始前に目的を手帳に書く(週3回) ・毎週目的の達成度と満足度を振り返る | ・3か月度で目的達成度70%以上 ・6か月後で満足度を30%アップ |
| 仮説を立てて練習法を選ぶ | 成果を効率的に出す | 新しい練習を始める前に仮説を1つ立てる | 半年後、練習効果を自己評価で+30%改善 |
| 趣味の目的を年初に再設定 | モチベーション維持 | 年初と半年ごとに目的を再設定 | 1年後、継続率90%達成 |
| 目的を「楽しむ」「上達」「癒し」で分類 | バランス良く充実させる | 各活動ごとに目的カテゴリを付ける | 半年で3カテゴリが満足度が高まるバランスになる |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家族イベントの目的を共有 | 誤解や不満を防ぐ | 予定を立てる際、目的を一文で共有 | 3ヶ月後、家族満足度アンケート+30%改善 |
| 家族会話で「今日は何をしたいか」目的を確認 | コミュニケーションを円滑にする | 夕食時に家族の目的を聞く(週3回) | 半年後、家族会話時間を20%増加 |
| 家事の目的を子どもと共有 | 自発的な行動を促す | 家事の理由を簡単に説明(毎日1回) | 3ヶ月後、自主的家事参加率50%達成 |
| 家族の仮説を立てて試す(例:休日の過ごし方) | 家族時間の最適化 | 月1回、新しい過ごし方を試す | 半年で「楽しかった」という感想を80%以上で得る |
①-2 情報収集力:信頼性の高い情報源を活用する/自ら多様な情報を取りに行く
目的や仮説を設定したら、情報収集に移りましょう。
その上で大事になるポイントは信頼性の高い情報源の活用と主体的で多様な情報収集です。
情報収集の質を決めるのは情報源の正確性です。目的にあわせて信頼性の高い適切な情報源の選択が鍵となります。
また、情報は待っているのみでは集まりませんし、得られる情報には偏りが生まれます。多様な視点で情報を収集するには主体的な情報収集が必要となります。
情報収集の質を高めるにはどうすればよいかを整理します。

情報収集の内、アンケートの取り方のコツについてはこちらをご覧ください!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 公的機関・学会・一次情報ソースを優先的に確認する | 情報の正確性を高め、誤情報による判断ミスを防ぐ | 毎日1件は信頼性の高い一次情報をチェック | 業務判断の根拠となるデータを常に3件以上提示できる状態にする |
| 情報発信者の背景や専門性を調べる | 情報の偏りや意図を見極める | 1日1回、参照した情報の出典を確認する | 3か月で情報の信頼度を自ら説明できるようになる |
| 同一テーマを複数ソースで照合する | 認知バイアスを防ぎ、バランス感覚を養う | 重要情報に対し、最低2つの別ソースで確認 | 情報を比較検証し、周囲へ客観的に説明できるスキルを確立する |
| 上司・同僚・他部署へ自ら質問・確認する | 能動的に情報を収集する姿勢を持つ | 毎日1回は他部署・他職種から意見や情報を得る | 半年で社内ネットワークを通じて必要情報を自力で収集できる体制をつくる |
| 社外セミナー・勉強会・Webinarへ定期参加する | 最新知識・業界動向をキャッチアップする | 月1回は業界情報に関するイベントに参加 | 1年後に情報感度の高い人材として周囲から相談されるポジションを築く |
| 実際に行動に移す | 行動に移すことで問いを具体化し情報の質を高める/仮説を検証する | ・毎週新たな行動に挑戦する ・月に1回重要なテーマに関する仮説を検証し、仮説を更新する | ・3か月で新たな取り組みを10個以上 ・半年で実行に移した仮説5個以上/目標達成率を20%アップ |
①仕事+α(発信や振り返りで情報精度を高める)
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 情報共有の仕組み(社内ノート・Teams・Slackなど)を活用する | 自分の収集情報を整理し、他者と共有する | 毎週1回、自分の得た情報を共有チャンネルに投稿 | 1年後、チーム全体の情報循環を促進するリーダー的存在になる |
| 「一次情報」「二次情報」を明確に分けて扱う | 情報の加工度を理解し、誤解を防ぐ | 情報引用時には必ず一次情報を参照する | 6カ月で業務資料・報告書で信頼性を担保した発信ができる |
| 得た情報を週1回まとめてレビュー | 情報の質を検証し、次に活かす | 毎週末に「今週の情報3選」を自分用に整理 | 情報整理と分析を習慣化し、改善提案につなげられる |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 部下育成に関する一次資料(学術論文・社内分析)を活用する | 根拠に基づいた判断・指導を行う | 週1回は一次情報・専門資料を確認する | 6カ月で育成方針の根拠をデータで説明できるようになる |
| 経営方針や業界ニュースを信頼性のあるメディアから収集する | 組織方針との整合性を保つ | 毎日10分、公式発表や業界情報をチェック | 3か月でチームに正確な方針を自信をもって共有できる |
| 部下・他部署との1on1で現場のリアルな声を聞く | 上層部と現場の情報ギャップを埋める | 週2回は異なる立場のメンバーと会話 | 現場感覚に基づいた意思決定ができる |
| 他リーダーや他社管理職と情報交換を行う | 視野を広げ、他組織の成功事例を学ぶ | 月1回は社外リーダーとの交流を持つ | チームの課題解決に外部知見を活用できる |
| 感情的・主観的な意見とデータを切り分けて整理する | 判断の客観性を担保する | 会議ごとに「事実・意見」を分類メモ | 6カ月でチーム全体に“ファクト思考”を浸透させる |
| チームミーティングで収集情報を共有・討議する | メンバーの学びと連携を促進 | 週1回、情報共有MTGを実施 | 6カ月でチーム全体が情報に強い組織文化を持つ |
公の情報源
ここで一般的に信頼性が高いと考えられる公の情報源を活用しやすさ順に紹介します。
| 情報源 | 具体例 | 特性 | 活用のコツ | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 公的機関の発表 | 政府省庁・統計局 (例:経産省、厚労省、内閣府) | 正確性・中立性が高く、公式な現状把握に適している | 数字の背景(定義・対象・範囲)を確認して適切なデータを選択する | 更新日が古いと意味合いが変わる、ユーザビリティは高くなく慣れが必要 |
| 専門機関・研究所 | 学会、大学、シンクタンク、論文 | 専門的・理論的な知見が豊富で深堀に有用 | 主体的に探しに行く、最新情報を自動的に入手する仕組みを作る | 独自の仮説や前提条件に基づくため、他ソースとの比較検証が必要 |
| 信頼できるメディア | 日経、BBC、ノーカットインタビュー | 情報の裏付けがされており、ニュース性と社会性に優れる | 編集の意図や政治的傾向もありえるので、複数のメディアをバランスよく活用する | アクセスしやすいメディア(国内、サジェスト)に偏らない |
| 業界団体・業界誌 | 協会・定期誌 | 実践的なトレンドや課題を網羅。専門性と実用性が両立 | データの出所が適切であるか、根拠の客観性をチェック | 支持団体なども確認し発言が偏っていないかに注意する |
| 専門家・有識者の発信 | 専門家の講演・書籍・SNS | 独自の視点や現場の治験が多く、洞察に富む 情報も早い | 抽象化することで汎用的なナレッジを得る | 個人の主観や商業的意図に注意し、根拠の有無や妥当性を注視 |
アプローチの種類
また、情報収集の上で活用できる主なアプローチも下記に紹介します。目的や必要な情報にあわせてアプローチを使い分けることが重要です。
| アプローチ方法 | 特徴 | 具体例 | 活用のコツ |
|---|---|---|---|
| 自主観察 周囲の動きや変化を観察し、そこから情報を読み取る方法。 | 最も手軽だが、主観に偏る可能性がある。普段のコミュニケーションが鍵。 | 日常会話や表情より変化を読み取る、現場に出向き直接観察する | 変化や気づいた点を記録しておく、主観的な解釈に頼らず事実を観察する |
| 組織調査 ログデーやアンケートから全体の傾向を読み取る。 | 量と網羅性が強みで定量的な情報を得やすい。目的に応じたシステムや調査方法のデザインが必要。 | 社内KPIダッシュボードを見る、システムのレポートを活用する、アンケートを実施する | 目的より情報を選ぶ、複数の情報源からバランスをとる、古い情報や誤情報に注意 |
| 双方向対話形式 相手とのやり取りを通して情報の確認や深掘りを行う手法です。 | 自分が気づかない視点や感情の裏側に気づきやすくなる。 | 1on1でヒアリングを行う、意見交換会やカジュアルランチで本音を聞く | オープンクエスチョンで背景や意図を引き出す、「なぜ?」を2回以上使い深堀する、結論を急がない |
| 組織的連携の活用 組織内外のネットワークから情報を得る手法。 | 広い視点で全体把握が可能になる。主体的な働きかけが必要 | 他部署との勉強会や交流会に参加、最新のプロジェクトチームに入る | 相手にも情報をギブする姿勢により情報をもらいやすくる、定期的な接点を作る |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 専門家・経験者のブログや公式サイトから情報を得る | 誤情報や偏りを防ぐ | 1日1件は公式・専門的情報を確認 | 正しい知識で趣味の質を高められる |
| SNS情報は複数ソースで確認してから採用する | 流言や誤解を防ぐ | 投稿を見たら必ず出典を調べる | 情報の真偽を見抜く判断力を養う |
| 同じ趣味のコミュニティで質問や交流を行う | 新しい知識や技術を得る | 週1回は他メンバーに質問や共有をする | 趣味仲間とのネットワークを広げる |
| ワークショップ・展示会・イベントに参加する | 体験から学びを得る | 月1回はリアルまたはオンラインイベントに参加 | 体験を通して継続的にスキルを高める |
| “自分の目的に合うか”で情報を取捨選択する | 情報過多を防ぎ集中力を維持する | 情報を得たら「今の自分に必要か、活用できるか」を考える | 趣味の方向性を明確に持ち、迷いを減らす |
| 習得した内容をSNSや日記にまとめて記録 | 知識の定着と他者貢献 | 趣味活動後に1行でも感想を残す | 自分だけの知見ログを構築し、共有文化を築く |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家事・育児・健康情報は公的機関や医療監修サイトを参考にする | 家族の安全と健康を守る | 毎回情報を使う前に出典を確認 | 家族に安心して共有できる知識を持つ |
| 金融・教育情報は公式・一次情報に基づいて判断 | 誤情報による損失を防ぐ | 重要情報は必ず複数ソースで確認 | 家庭運営におけるリスク判断力を高める |
| 配偶者や子どもの意見・希望を直接聞く | 家族の本音を理解する | 毎日1回は「今日どうだった?」と尋ねる | 家族間の信頼・対話の質を高める |
| 学校・地域・PTAなどに積極的に参加 | 子どもや地域のリアルな状況を知る | 月1回は学校・地域行事に関わる | 家庭外の情報ネットワークを築く |
②-1 情報を分類・整理する(フレームワーク活用・構造化・優先順位条件整理)
情報を集めたら次は活用しやすいように情報を分類・整理することが必要です。このステップが上手く行くことで意思決定の質が上がります。また、情報の漏れや情報の洪水に翻弄されることも回避できます。
フレームワークや構造化など、情報活用しやすくするにはどのような分類・整理のコツがあるかを考えていきましょう!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 5W1Hを用いて情報を整理する | 業務課題の明確化と要点把握 | 毎日1件の報告・課題に対して5W1Hで整理 | ・3か月で情報の網羅率を20%向上 ・6か月で業務改善提案数を5件以上 |
| マインドマップで課題全体を可視化 | 情報の漏れ防止と関連把握 | 週1回テーマをマインドマップ化 | 半年で課題抽出の網羅率80%達成 |
| ロジックツリー、5Whysで原因追及 | 問題の本質を明確化/根本原因を特定 | ・毎月課題をロジックツリーで掘り下げる ・トラブル発生時に5Whysを使って再発防止対策 | ・3か月で業務改善提案数を2件以上増加 ・半年で課題再発率を30%削減 |
| パレート分析で主要課題を抽出 | 成果を出す要因を明確に | 月1回業務成果を20:80視点で振り返る | 半年後、業務改善効果指標10%向上 |
| アイゼンハワーマトリクスで優先順位づけ | 効率的な行動管理 | 毎朝タスクを4象限で分類 | 3か月後、重要タスク対応率90%維持 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| チーム内の情報をテーマ別に分類 | ルール明確化/仕組み化により情報共有の質を向上 | 週1回、会議情報をテーマ分類で共有 | 半年で報告漏れを50%削減 |
| フィッシュボーン図で課題原因を共有 | メンバーの理解促進 | 月1回チーム課題を図示してディスカッション | 半年でメンバー提案数を2倍に |
| 優先順位会議を定例化 | チーム判断の明確化 | 毎週15分の優先順位見直しミーティング | 半年でタスク遅延率30%減少 |
| 情報の網羅表を作成 | 抜け漏れを防ぐ | ・プロジェクト開始時に5W1H×重要度表を作成 ・3か月に1度項目と重要度の修正を検討 | 3か月で計画修正回数20%減 |
| 構造的に業務を俯瞰 | 部下支援と進行管理の効率化 | 毎週プロジェクト構成をマッピング | 半年でチーム目標達成率90%維持 |
| 知見共有会を開催 | 情報の水平展開 | 月1回、学びを共有する会を開催 | ・半年で共有テーマ数6件以上達成 ・1年で具体的な業務改善効果に繋がる事例共有を7件以上 |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 趣味の計画を5W1Hで整理 | 時間と費用を有効に使う | 月1回、活動計画を5W1Hで可視化 | ・半年で達成率80%維持 ・1年で趣味の満足度(リソースの有効活用率)30%アップ |
| マインドマップでアイデアを展開 | 情報・思考を整理しながら発想の広がりを促進 | 月2回新しいアイデアをマインドマップ化 | 3か月で新挑戦3件実施 |
| 優先順位を数値化 | 楽しみのバランスを最適化 | 月1回タスクを重要度5段階で評価 | 半年で満足度セルフアンケート平均4.0以上 |
| 5Whysで失敗原因を整理 | 次回の改善に活かす | 失敗時に必ず5Whys記録 | ・半年で改善のための新規と取り組みを5件以上 ・1年で同様失敗率50%削減 |
| 俯瞰してテーマ別に整理 | 趣味の全体像を把握 | 週末に全活動を1枚にまとめる | 半年で活動継続率90%維持 |
| フレームワークを使った振り返り | 継続と成長を促進 | 月末に振り返りを「Keep/Problem/Try」で整理 | 半年で改善項目6件達成 |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家事や予定を5W1Hで整理 | 役割分担を明確にする | 週1回家族会議で予定を整理 | 半年で家事トラブル件数50%減 |
| マインドマップで家族イベント計画 | 家族間の理解と共有促進&計画段階から楽しむ | 月1回イベント案を家族で作成 | 1年で実行イベント数6件以上 |
| アイゼンハワーマトリクスで優先づけ | 家庭時間を最適化 | 毎週末、家族予定を重要度順で整理 | 半年で家族時間の満足度4.5以上 |
| ロジックツリー等で支出を視覚化し見直し | 家計管理の効率化 | 月1回支出を分類し可視化 | 半年で無駄支出10%削減 |
| 家族内情報共有ボードを運用 | 情報の見える化 | 毎日1回予定ボードを更新 | 3か月で予定漏れゼロ継続1か月以上 |
②-2 情報を分析する:因果関係の理解・仮説検証・優先順位設定
情報整理の次は分析の段階です。具体的には、因果関係/相関関係の特定や仮説検証、優先順位の決定などに情報を活かして情況把握を深めます。
それでは、情報をいかに効率よく活かすかというコツを見ていきましょう!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| PDCAを小さく早く回す | 改善の精度と速度を上げる | 毎日1件の業務にPDCAを適用 | 半年で改善提案件数を10件に |
| 仮説を立ててから情報を集める | 無駄な調査を防ぐ | 毎回の課題に「仮説→検証」メモを残す | 3か月で検証精度を70%以上に |
| 仮説検証の結果をチーム共有 | 組織知として蓄積 | 毎月1回共有会で学びを発表 | 半年でナレッジ共有数6件以上 |
| KPI/KGIの因果関係を整理 | 結果を左右する要因を明確化 | 週1回、KPI進捗と要因を整理 | ・3か月でKGI, KPIに繋がる重要な因子を特定 ・半年で主要KPI達成率90%以上 |
| 問題を「原因・影響・対策」で構造化 | 課題解決の抜け漏れ防止 | 週1件、報告書を3層構造で作成 | 半年で再発課題30%減 |
| 優先順位をデータで判断 | 感覚に頼らない意思決定 | 週次報告で定量指標を根拠に提示 | 半年で判断ミス20%減 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 部下の行動結果を要因別に分析 | 育成精度を上げる | 1on1ごとに成果要因を3分類 | 半年で育成計画達成率80%以上 |
| 半年で育成計画達成率80%以上 | メンバーの理解を促進し、行動指針を示す | 月1回、チーム会議で因果図を提示 | 半年で全員がKPIを説明可能に |
| 仮説検証型の進捗報告を導入 | 改善速度を上げる | 各メンバーに週1回仮説検証報告を依頼 | 半年でチーム改善提案数2倍 |
| チーム課題の仮説会議を実施 | 多面的な視点を養う | 月1回仮説ブレスト会を開催 | 半年で提案採用率40%超 |
| 優先順位の基準を可視化 | 判断の透明性向上 | プロジェクトごとに評価軸表を更新 | 半年で納期遅延率30%減少 |
| フィードバックを「原因・行動・結果」で伝える | 成長の再現性を高める | 1on1で毎回この構造を使う | 3か月で改善行動率70%達成 |
相関関係/因果関係を区別する
分析において特にコツが必要なのが、相関関係と因果関係の区別です。
因果関係を明確にすることでその事象が起きた原因を特定でき、再発防止や改善策に繋がります。根本原因を正しく捉えることで真に効果的な施策設計が可能になります。
しかし、一見因果関係に見えても直接的な繋がりがないことは珍しくありません。ここで、相関関係/因果関係の区別をするためのアプローチやポイントを振り返ります。
相関関係を見つける
まず相関関係とは連動した動きを見せる関係のことです。
因果関係の特定の上で紛らわしい存在である相関関係。ただ相関関係単体でも意味があります。類似パターン間の共通点を確認することで潜在するカギとなる因子を洗い出すことができます。
相関関係を見つけるには複数の変数を組み合わせてデータを集計・分析するクロス集計や2つの項目を縦軸と横軸にプロットする散布図により調べることができます。客観的に関係性を把握する上では近似線を引いて相関係数を活用しましょう。
相関関係が見つからない場合は極端な外れ値が無いか確認して処理しましょう。また全体で相関が見つからない場合は母集団や時系列を分けて分析することで隠れた関係性が明らかになることがあります。
因果関係を特定する
次は因果関係の特定です。この特定には5Whysで原因を深掘りしたり、ロジックツリーやフィッシュボーンで主原因・副原因を可視化して構造的に整理することが有効です。
分析の上での注意点は、第三の要因(季節や年齢など他の直接的要因)がないか、実際にデータは連動しているか、因果が逆転していないか(実は結果と思っていたものが原因ではないか。例えば、年収と健康の関係など)となります。
また、「課題発見力」の回で紹介した下記の質問も因果関係の精査に役立ちます。
| 質問の種類 | 期待できる効果 | 具体例 |
|---|---|---|
| 5Why分析の質問(なぜを繰り返す) | 表面的な原因ではなく、根本的な課題を見つける | 「売上が下がった → なぜ? → 広告のクリック率が低下 → なぜ?」 |
| データ確認型の質問(数値での裏付け) | 感覚的な判断ではなく、データに基づいた分析ができる | 「問い合わせが増えたと感じるが、実際の件数はどうなっているか?」 |
| 関係性を問う質問(相関関係 vs 因果関係) | 2つの事象のつながりを考え、誤った因果関係を避ける | 「新商品の売上が伸びたのは、広告の影響なのか?他の要因は?」 |
定性データのみでなく定量データや時間的相関を確認し、因果関係が本当に成立しているかを精査することを意識しましょう。
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 成果と行動の関係をメモする | 成長の因果を理解 | 活動後に「やったこと・結果」をセットで記録 | 半年で上達実感スコア+30% |
| 小さな仮説を立てて試す | 改善を楽しむ習慣化 | 月2回、新しい方法を試す | 半年で成功法3件発見 |
| 優先度を「成長・楽しさ」で整理 | モチベーション維持 | 月1回活動計画を2軸評価 | 半年で継続率90%維持 |
| 振り返りで原因を3つ挙げる | 思考の整理と改善促進 | 毎回活動後に3原因メモ | 3か月で課題解決率50%超 |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家族トラブルを原因・結果で整理 | 感情的反応の抑制 | 問題時に要因を3分類 | 半年で再発率50%減 |
| 家事分担の見直しを仮説検証 | 負担の公平性向上 | 週1回実験的変更を実施 | 半年で不満件数半減 |
| 優先度を家族全員で決める | 価値観の共有 | ホワイトボード等を活用して月1回家族ミーティング実施 | 半年で合意形成率80%以上 |
| 行動と結果を一緒に振り返る | 学び合う文化醸成 | 月1回家族会で「うまくいった理由」を共有 | 1年で家庭会議定着率100% |
3.俯瞰力・適応力:全体を広く捉え、変化に応じて視点や行動を調整
情報を整理・分析の後、まずは整理・分析した情報を統合して俯瞰して情況を把握する力が求められます。そして、視点や行動を調整する適応力が情報の活用のカギとなります。
変化・適応する力が無ければ折角得られた情報も宝の持ち腐れです。この要素を強化することでバランスよくここまで収集・整理した情報をバランスよく活用して柔軟に変化に対応することが可能となります。
具体的に全体像を捉えて把握した情況を行動に取り入れるための推奨行動を考えていきましょう!
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 上流から下流まで全体をマップ化 | 全体最適で行動する | 月1回業務フローを俯瞰図化 | 半年で全体効率10%改善 |
| ステークホルダーの立場で考える | 調整力の向上 | 週1回他部署、依頼者目線で情報を整理しての振り返り | 半年で関係者満足度4.5以上 |
| 代替案を常に2つ用意 | 柔軟な判断力を鍛える | 毎回提案に+1案添える | 半年で採択率30%向上 |
| 想定外を「想定内」に変える訓練 | リスク対応力の強化 | 週1回整理した情報から考えるリスクを用いて「if思考」で準備 | 半年でトラブル対応時間30%減 |
| 自分の立場を一歩引いて見る | 冷静な判断を維持 | 毎日1回、俯瞰視点でメモ | 3か月で衝動的判断ゼロ週継続 |
| 新しいやり方を試す | 変化対応力を高める | 特定した課題に対して月1回業務プロセスを改善 | 半年で新提案5件採用 |
| 思考を切り替える練習をする | 視点を変え柔軟な思考力を高める | 6色ハット思考法等で異なる視点で物事を考える時間を毎週設定する | 3か月で複数視点で考える癖が習慣化 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| チーム全体の関係図を可視化 | 連携構築の効率化 | 月1回関係マップ更新 | 半年で連携ミス50%減 |
| 全体のバランスを考える | 俯瞰的な視点から最適解を考える | スライド思考を活用し、具体と抽象の両面で対象を深掘りする | ・3か月で本質を考える習慣が定着 ・6カ月で視点不足による判断の誤りが30%低下 |
| 複数視点で評価する | 公平な判断を徹底 | 評価時に3視点(ステークホルダー、顧客、社会など)を確認 | 半年でステークホルダー納得度80%超 |
| 「なぜ今この方針か」を説明 | 意図の共有 | 会議で毎回背景と取り組みの意図を説明 | 半年で方針理解率90% |
| 想定外に柔軟対応 | チームの安定性維持 | 毎回トラブル対応を振り返り | 半年で対応時間20%短縮 |
| 未来シナリオを3通り考える | 戦略的思考の育成 | 月1回得られた情報を活用して3パターン想定 | 半年で計画達成率90%維持 |
| 未来志向でリスクを考える | リスクを明確化して対策を事前に検討する | 現在の計画が最も失敗した場面を想定し、その際の原因を分析して対策を考える | ・3か月で事前のリスク特定率を30%アップ ・1年で事前対策によるリスク軽減が30%アップ |
| 自身の立場と部下の立場を入れ替えて考える | 共感的判断を育てる | 1on1で月1回立場入替質問 | 半年で信頼スコア+20% |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 全体計画を可視化する | 継続と達成感の両立 | 月1回年間計画を更新 | 半年で実行率80%以上 |
| 複数視点から作品を評価 | 柔軟な受け止め方を鍛える | 月2回他人の視点でレビュー | 半年で満足度+25% |
| 想定外を楽しむ姿勢を持つ | 心の余裕を育む | 活動ごとに1回「想定外を楽しむ」発言 | 半年で継続率90% |
| 過去・現在・未来を俯瞰して考える | 成長を実感 | 月末に3期間レビュー | 半年で目標達成件数+3 |
| 自分の成果を客観視する | 成長課題の把握 | 活動ごとに1行感想記録 | 半年で改善達成率70%超 |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 家族全体の視点で考える | バランスの取れた判断 | 週1回家族全員視点で議題整理 | 半年で衝突件数30%減 |
| 相手の立場に立って話す | 共感と理解の促進 | 毎回対話で1度は「相手視点」で要約 | 半年で会話満足度4.5以上 |
| 家族計画を俯瞰して整理 | 長期的幸福の実現 | 月1回年間計画を見直し | 1年で実行達成率85% |
| 想定外を柔軟に受け止める | 余裕ある家庭運営 | 想定外時に深呼吸→再調整 | 半年でストレス実感20%減 |
| 問題を客観的に話し合う | 感情的衝突を防ぐ | 問題時に第三者視点質問を1回 | 半年で問題再発ゼロ |
4.情報を基にした判断・決断力
最後に情報を基にどのように判断・決断をするアプローチを考えます。情況把握力を使いこなす最後の鍵として、収集して分析した情報を実際に活用するためのコツを整理します。
①仕事
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 判断前に3種類以上の情報ソースを照合する | 感情的判断を防ぎ、根拠ある決定を行う | 判断前に3種類以上の情報ソースを照合する | 3か月以内に意思決定のエラー率を20%削減 |
| 情報の信頼性を3段階で評価 | 誤情報を排除 | 入手した主な情報を「高・中・低」で分類 | 6か月以内に情報誤用ゼロを達成 |
| 情報を「重要度×確実性」でマッピング | 判断材料の優先順位を明確化 | 毎回判断前に情報を2軸整理 | 半年で意思決定の根拠資料提示率を100%に |
| 定量情報と定性情報を組み合わせて考える | 客観性と現場感の両立 | 週1件の提案で数値+現場事例をセット化 | 6か月以内に提案採用率を30%向上 |
| 過去のデータと傾向を参照して仮説を立てる | 再現性の高い判断を実現 | 類似案件の3件分を参考に仮説を設定 | 1年以内に仮説通りに進行した案件率70%達成 |
| 判断に使用した情報の出所を明記する | 信頼性と説明責任を確保 | 判断文書に情報出典を明記する | 半年以内に「根拠明示のある決断」比率を80%に |
| 判断後の結果をデータで検証 | 次の判断精度を高める | 週1回、意思決定結果の数値を振り返る | 1年で意思決定後の修正発生率を30%削減 |
②リーダー
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| メンバーから現場情報を週1回収集 | 現場感を踏まえた判断を行う | チーム全体の情報を定例で共有 | 半年で判断精度に関するFB満足度を80%以上に |
| 情報を「影響度×緊急度」で可視化 | 優先順位を客観的に決定 | 課題を2軸マトリクスで整理 | 3か月以内に決定スピードを20%向上 |
| 判断基準を明文化して更新 | 感情的判断を防止 | 月1回、基準を見直しメンバーに展開 | ・半年で意思決定のブレによるトラブル半減 ・1年間で判断基準へのメンバーの納得感90%以上 |
| 重要判断前に2名以上の異なる視点を確認 | バイアスを排除 | 会議で立場の違うメンバー意見を聴取 | 半年で誤判断発生率を25%減 |
| データと感覚をバランスして判断 | チーム納得度を高める | 意思決定時に「数値+感覚コメント」をセット化 | 6か月以内に決定後の不満率を20%減 |
| 判断に使うデータをグラフ化 | 視覚的に納得感を得る | 週1回成果を可視化して判断材料に | 1年後に自作分析資料が10件以上に到達 |
| 情報を整理したロジックツリーで説明 | 理解促進と再現性の確保 | 判断時に論理構造を可視化 | 半年以内に判断理由を理解できる率90%達成 |
| チーム判断を定量評価して共有 | 判断の改善サイクルを作る | 月1回、決定→成果を数字で見える化 | 1年でチーム成果の計画達成率を15%向上 |
③趣味
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 新しい挑戦時は3件以上の参考事例を調査 | 試行錯誤の効率化 | 挑戦前に成功・失敗事例を比較 | 半年以内に失敗率を40%削減 |
| 活動データ(時間・結果)を記録して分析 | 判断の客観性を持つ | 練習内容と成果をセットで記録 | 3か月で改善施策成功率を25%UP |
| 他者の経験から意思決定パターンを学ぶ | 自分の判断の幅を広げる | 月1回、他者の振り返り記録を読む | 半年以内に判断の多様性が3倍に増加 |
④家庭
| 推奨行動 | 目的 | 日々の行動目標 | 中長期的達成目標 |
|---|---|---|---|
| 判断前に感情と事実を分離して整理 | 冷静な判断を維持 | 意見が分かれたらまず“事実3点”を確認 | 半年以内に感情的対立件数を50%減少 |
| 過去の家庭データを基に判断 | 再現性と合理性を高める | 家計簿や日記を参照して判断 | 1年以内に「後悔なし判断」比率を80%に |
| 家族会議で情報を可視化して検討 | 主観を減らし客観的に決める | ホワイトボードやアプリで比較検討 | 半年以内に会議での決定満足度80%達成 |
| 子どもにも情報を渡し選択させる | 自律的判断力の育成 | 日々の選択に理由を説明して決めさせる | 1年以内に子の自主判断場面を週3回以上に増加 |
おわりに
「情況把握力」は、社会人としての基礎的なスキルであり、日々の業務や人間関係において重要な役割を果たします。
この力を高めることで、より円滑なコミュニケーションや効果的な業務遂行が可能となります。ぜひ、日常の中で意識的に情況把握力を鍛え、実践してみてください!
それではまた次の記事で!